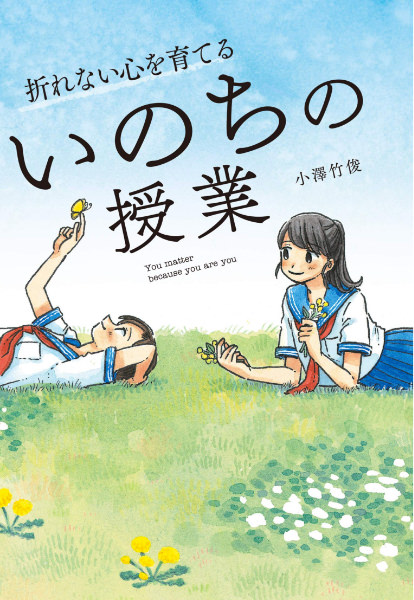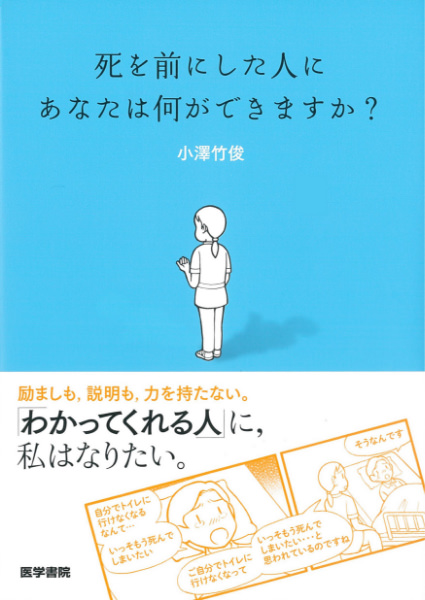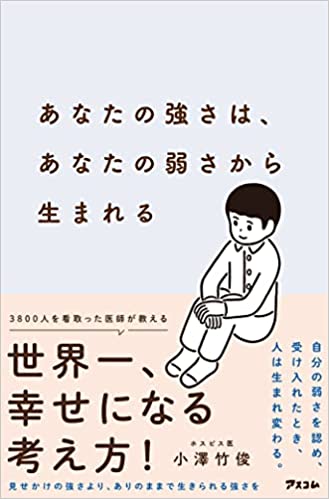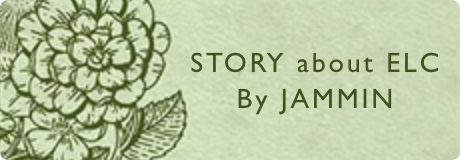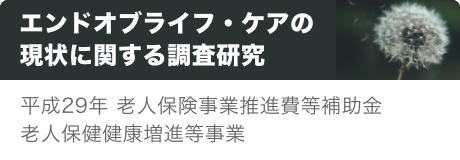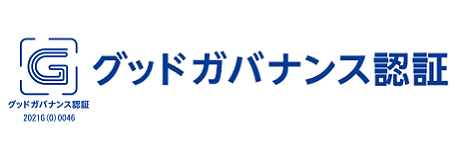地域学習会 開催レポート
Study Group Report
-
ELC沖縄 地域学習会
2019.10.13
-
由仁エリア看取り塾
2019.10.12
看取りの利用者様とご自宅で過ごしたいとご本人、ご家族が増えていますが、訪問診療、訪看と医療系のサービスの不足が課題です。 繰り返しの訓練が必要と思います。いろいろな職種で事例検討が勉強になりました。 ロールプレイの聞き役が難しく思いました。訓練することで成長できるだろうと思いました。いろいろな場
-
ー
2019.10.11
-
エンドオブライフ・ケア
2019.10.11
-
演題:苦しむ方への援助 副題:苦しんでいる人は自分のことをわかっている人がいるとうれしい
2019.10.11
-
ELC紀州第1回学習会 援助的コミュニケーションとディグニティセラピー~大切な人への手紙~
2019.10.10
-
第7回 ELC奈良学習会
2019.10.08
-
ディグニティセラピーワークショップ
2019.10.05
-
エンドオブライフ・ケア~苦しむ人への援助と5つの課題~
2019.10.05
これまで、励ましたり、何か言わないとと思っていたけれどもそうではないことがわかった。早速、実践してみようと思う。ディグニティセラピーに関心を持った。 患者さんは自分たちをよく見てくれている。 受付は医療者ではないけれども、一番はじめに話を聴くところだから、表情をよくみようと思う。家族の話もこのよ
-
紀南病院勉強会(第31回紀南多職種連携研修会)『心のケア研修会 ~「もしバナゲーム」と「支えの話」~』
2019.10.04
・自分には支えの関係にあると思える人がいないことに気づいた。援助者として勉強し苦しんでいる人の力になれるようになりたいと思った ・医療者側の都合を押し付けるのではなく、患者さんの希望にそった看護ができればと思います。 ・家族がありがたい存在だと知った ・病息の夫に対して、今までの対応を反省し、
-
ターミナルケア~苦しむ人への援助と5つの課題~
2019.10.02
いつも、困ったことはないかと尋ねていたことを振り返った。話をよく聴き、その人の支えをみつけてゆきたいと思った。 日頃、事例検討すると、サービスのことばかり考えていたなと思った。 他の人の話や他のグループの援助を聴いたとき、同じことでもそれぞれに価値観が違うと違う援助になるんだなと思った。 楽し
-
「エンドオブライフ・ケア研修~死を前にした人に私たちのできること~」
2019.09.29
チェックアウト・シートから; 市内の薬剤師対象。薬剤師は、患者が内服困難となるため、在宅看取りに関われないという誤解を聞いたことがあるが、今回の参加者は、援助の対象や考え方について十分理解していて、反復と沈黙の効果の実感から、「聴くモード」の重要性を理解していた。
-
(仮)2019年度 第1回 ELCよこすか学習会
2019.09.28
○事例を通したものですと、イメージしやすく良いかと思います。 ○復習できた気持ちになりました。なっただけにならい様、実践します。 ○少人数でアットホームな感じでリラックスして学ぶことができました。
-
ゆたかな人生を支えるエンドオブライフ・ケアとACP~誰かをささえようとするひとを支える援助とは何か~
2019.09.27
-
エンドオブライフケア~人生の最終段階に関わる私たちができること~
2019.09.26
・自分のできる援助はどこまでも相手の捉え方次第なんだなあと難しいなと思いました。 ・ロープレが結構難しかった。どこまで言っていいのか迷うところもあった。 ・解決できない相談の返答に対して、理解者になるということを学べて良かったです。 ・声かけや関わり方をイメージで教えていただけたので、理解しや
-
人生の最終段階に関わる「苦手意識」を「関わる自信」へ変える援助的コミュニケーション
2019.09.26
・コミュニケーションで気まずくなることがあり、苦手意識があったため学習会に参加しましたが、沈黙により相手から本心が引き出せることもあるという点が印象的でした。 ・何となくやっていたことが文章化されたことでその大切さがわかった。 ・大切なことをうちあけてくださったときに反復をしていたなぁと思い出す
-
苦手意識を関わる自信へ~終末期・急変時の対応について~
2019.09.26
-
今、『苦しむ人への援助とは』わかってくれる人に、わたしはなりたい!【SWが直面する意思決定支援と、決定後の具体的援助まであなたはわかりやすい言葉で周りの方々と話すことが出来ますか?~Let's Try ELC!!~】
2019.09.22
-
第3回 ELCさいたま フォローアップ学習会
2019.09.21
-
親のこと、自分のこと、これからのこと ~人生のおわりから考える~
2019.09.20
-
ー多職種で考える看取りの関わりー
2019.09.19
-
エンドオブライフケア学習会〜支えたいのに「いっそ死にたい」と言われ返す言葉がみつからない・・・〜
2019.09.19
-
3回連続開催予定 ①援助的コミュニケーションを学ぼうⅠ
2019.09.19
-
#11エンドオブライフケア糸島唐津
2019.09.15
*「私が」が主語だと本当に苦しいけれど「相手」と思えるとこれでいいと認めることが出来る。次回の学びも楽しみにしています。 *少人数で意見や質問もしやすくとても充実したものになったと思います。リピーター枠に参加しましたが5人だけでは勿体ないなと思いました。 *事例のことが、今後発表に出たことを実現
-
多職種で行うエンドオブライフ・ケア研修 〜聴く力〜「苦しむ人へ関わるための援助的コミュケーション」
2019.09.14
-
第3の課題『相手の支えをキャッチする』
2019.09.14
「尊厳」などを考えたことが無かった。自分の大切にしていることは何だろう?と考えるきっかけを与えられた。 自分の支えとなる関係を他の人に話すのはためらう気持ちがあった。
-
「エンドオブライフ・ケア~人生の最終段階の苦しみを抱えた人に何ができますか?~」
2019.09.10
チェックアウト・シートから; 2時間という制約もありながらも援助的コミュニケーションの効果について理解が得られたが、つねに「人生の最終段階」にある入所者に接している職種としては反応はいま一つであった。 「苦しむ人への援助」という視点を強調する進め方も必要だったかも知れない。
-
もしもの時の話し合い もしバナゲーム&苦しむ人への援助と5つの課題
2019.09.08
・人生の最終段階に関わるケアとして、負のメッセージに対する声かけに苦手意識、難しいと感じていました。 今回の研修に参加し、反復や沈黙、支えについての引き出し方を学ぶことができたかと思います。 ・日々トレーニングが必要だと感じました。お世話になりました。 ・「苦しさから多くの事が学ぶことができ
-
「エンドオブライフ・ケア~人生の最終段階の苦しみを抱えた人に何ができますか?~」
2019.09.08
チェックアウト・シートには、診療所、施設、病院、通所・訪問介護事業所の介護職員が対象、一部、地域学習会受講者。 「解決できない苦しみ」や「苦しみを抱えたまま穏やかになる可能性」、 「支え(を強める)」などの援助の考え方の受け入れ、聴くことの難しさと、効果についての(実践に繋がりそうな)実感が表明
-
苦しむ人と向き合うために
2019.09.08